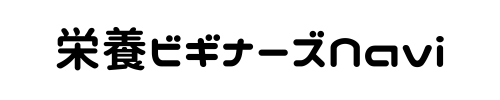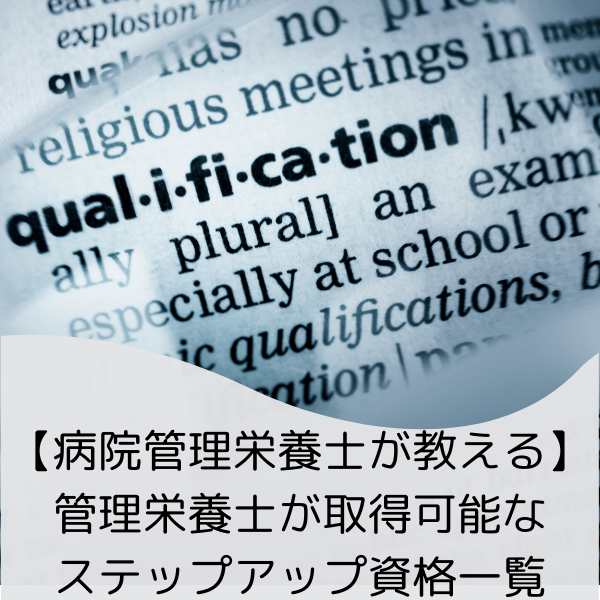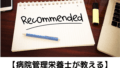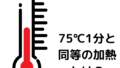管理栄養士として、病院や施設で働いていると様々な資格を持った管理栄養士やMRを見かけると思います。
管理栄養士が目指すことができるステップアップ資格はたくさんありますが、今回は病院や施設など、医療介護の分野で役に立ちそうな資格を一覧としてまとめましたので、参考に頂ければと思います。
たまたま知った資格の取得を目指すよりも、どんな資格があるか知った上で、心惹かれる資格の取得を目指すのもよいのではないでしょうか。
本内容は、2024年3月時点の情報をもとに作成されています。詳細については必ず対象団体の公式ホームページでご確認いただきますよう、よろしくお願いいたします。
ではいきしょう。
- 日本栄養士会認定資格
- 管理栄養士・栄養士及びその他医療関係職種が取得できる資格
- 国家資格が不要な資格
- さいごに
日本栄養士会認定資格
●認定団体 公益社団法人 日本栄養士会
日本栄養士会では、認定管理栄養士・認定栄養士制度にて数多くのステップアップ資格が取得可能です。数多くの認定制度がありますので、リンクより詳細をご確認ください。一部病態栄養学会資格と交差するものもあります。
認定管理栄養士・認定栄養士
認定管理栄養士、認定栄養士は、各分野において「栄養の指導」について責任をもって実践できるレベルに到達したスキルを認める制度です。
- 臨床栄養
- 学校栄養
- 健康・スポーツ栄養
- 給食管理
- 公衆栄養
- 地域栄養
- 福祉(高齢・障害、児童)栄養等
- 実務経験 5年以上
- 研修 基幹教育60単位※臨床栄養70単位(実務研修+基本研修30単位)
- 入会の必要性 あり
- その他 キャリアシート作成、学会発表・参加要件あり
詳細は >>>認定管理栄養士、認定栄養士 認定制度 をご確認ください。
特定分野別 認定制度
特定分野における実践活動により、優れた成果を生むことができる管理栄養士を認定。
上記「分野」のリンクよりご確認ください
専門分野別 認定制度
さらに専門性を身に付けたい管理栄養士の方へ時代のニーズに応えるスペシャリストを認定。
上記「分野」のリンクよりご確認ください。
尚、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士取得には、日本摂食嚥下リハビリテーション学会「日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士」が必要です。
詳細は 日本栄養士会ホームページ をご確認ください。
管理栄養士・栄養士及びその他医療関係職種が取得できる資格
介護支援専門員(ケアマネージャー)
よく「ケアマネ」と呼ばれるのがこの資格です。持っていると活躍の場がとても広がるため、人気のある資格でもあります。受験資格を得るには管理栄養士取得後5年以上かつ相談援助業務を900日以上経験しないといけないため、取得を希望する方は計画的に準備を進める必要があるでしょう。
A及びBの期間が通算して5年以上であり、かつ、当該業務に従事した日数が900時間以上を有する者
A:医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士、介護福祉士、視能訓練士、義肢装具士、歯科衛生士、言語聴覚士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、栄養士(管理栄養士含む)、精神保健福祉士
B:相談援助業務
上記は詳細、説明を省略しています。詳細については、https://www.sssc.or.jp/shien/index.htmlを必ずご確認ください。
詳細は >>>各都道府県の担当部署ホームページ をご確認ください。
NST専門療法士
●一般社団法人 日本栄養治療学会
jspen(ジャスペン)という呼び名でおなじみの日本栄養治療学会が認定する資格。管理栄養士のみならず、看護師、薬剤師など栄養サポートに関係する医療関係職種から人気のある資格です。資格取得にあたっては40時間実地研修が必要ですが、他の病院の実際の栄養管理を学ぶことができるため、座学だけでは得られない生きた知識を勉強することができます。
- 実務経験 当該国家資格により3年以上、医療・福祉施設に勤務し、当該施設において栄養サポートに関する業務に従事した経験を有すること
- 研修 40時間実地研修が必要
- 入会の必要性 あり
- その他 本学会学術集会(10単位)1回以上+本学会主催の受験必須セミナー(10単位)+その他=30単位以上
NST専門療法士取得後、上位資格である「栄養治療専門療法士」を目指すことができます。
- 9領域から1領域限定(がん、肺疾患、肝疾患、腎疾患、リハビリテーション、在宅、小児領域、摂食嚥下、周術期・救急集中治療専門)
詳細は >>>日本栄養治療学会ホームページ をご確認ください。
病態栄養専門管理栄養士
●認定団体 一般社団法人 日本病態栄養学会
病態栄養専門管理栄養士
- 実務経験 医療機関で2年以上の業務(栄養管理)経験を有すること
- 研修 10単位以上
- 入会の必要性 あり(2年以上)
- その他 栄養管理に関する1症例のレポート提出
NSTコーディネーター
- 実務経験 医師または病態栄養専門(認定)管理栄養士であること
- 研修 10単位以上
- 入会の必要性 あり(2年以上)
- その他 NSTチームとして栄養評価を検討した自経3症例提出
がん病態栄養専門管理栄養士
- 管理栄養士として3年以上
- 1000時間実地修練(実地修練認定施設300時間+自施設700時間)
- 研修 30単位以上
- 入会の必要性 あり(2年以上)
- 自経5症例提出
- 病態栄養専門(認定)管理栄養士または臨床栄養認定管理栄養士であること
腎臓病病態栄養専門管理栄養士
- 研修 20単位以上
- 入会の必要性 あり
- 自経2症例提出
- 病態栄養専門(認定)管理栄養士または臨床栄養認定管理栄養士として1年以上
- 筆頭発表1回
糖尿病病態栄養専門管理栄養士
- 研修 20単位以上
- 入会の必要性 あり
- 自経2症例提出
- 病態栄養専門(認定)管理栄養士または臨床栄養認定管理栄養士として1年以上
- 筆頭発表1回
肝疾患病態栄養専門管理栄養士
- 研修 肝疾患病態栄養専門管理栄養士セミナーを1回受講
- 単位 20単位
- 入会の必要性 あり(日本病態栄養学会並びに日本栄養士会)
- 自経2症例提出
- 病態栄養専門(認定)管理栄養士または認定管理栄養士を取得していること
- 肝疾患に関わる栄養管理・指導に、通算1000時間以上従事していること
詳細は >>>日本病態栄養学会ホームページ をご確認ください。
臨床栄養師
●認定団体 日本健康・栄養システム学会
- 認定講座 100時間
- 臨床研修 900時間
- 認定試験あり
- 論文審査あり
- 当学会への入会必要
詳細は >>>日本健康・栄養システム学会ホームページ をご確認ください。
腎臓病療養指導士
●認定団体:日本腎臓病協会
看護師、保健師、管理栄養士、薬剤師
- 実務経験 3年以上
- 研修 5年以内の腎臓病療養指導士認定のための講習会受講
- 入会の必要性 なし
- その他 過去10年以内に通算2年以上、かつ通算1000時間以上腎臓病患者の療養指導業務に従事している
詳細は >>>日本腎臓病協会ホームページ をご確認ください。
糖尿病療養指導士(CDE)
糖尿病療養指導士(CDE:Certification Board for Diabetes Educators)には、日本糖尿病療養指導士認定機構が認定する「CDEJ:日本糖尿病療養指導士」と各地域の認定団体が認定する「LCDE:地域糖尿病療養指導士」があります。それぞれ認定団体や受験資格が異なりますので注意が必要です。
日本糖尿病療養指導士(CDEJ)
●認定団体 一般社団法人 日本糖尿病療養指導士認定機構
看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士
- 実務経験 条件を全て満たしている医療施設において、過去10年以内に2年以上継続して勤務し糖尿病患者の療養指導業務に従事した方で、かつこの間に通算1,000時間以上糖尿病患者の療養指導を行ったこと
- 研修 本機構が開催する講習(eラーニング)の受講を修了していること
- 入会の必要性 なし
- その他 糖尿病療養指導の自験例10例以上
詳細は >>>日本糖尿病療養指導師認定機構ホームページ をご確認ください。
地域糖尿病療養指導士(LCDE,CDEL)
CDEJ以外にも、各地域に根差したCDEがあります。経験や条件など異なりますので、所管の公式HPをご確認ください。
健康運動指導士
●認定団体名 公益社団法人 健康・体力づくり事業財団
●健康運動指導士とは、個々人の心身の状態に応じた、安全で効果的な運動を実施するための運動プログラムの作成及び指導を行う者 健康・体力づくり事業財団HPより一部抜粋
104単位コース:4年大卒以上の歯科医師、看護師、准看護師、助産師、薬剤師、栄養士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、理学療法士、作業療法士、臨床検査技師
70単位コース:医師、保健師、管理栄養士
51単位コース:4年制体育系大学卒業者
40単位コース:健康運動実践指導者の称号を有するもの、日本スポーツ協会公認資格、日本フィットネス協会公認資格を有するもの
上記は詳細、説明を省略しています。詳細については、こちらを必ずご確認ください。
詳細は >>>健康・体力づくり事業財団ホームページ をご確認ください。
心臓リハビリテーション指導士
●認定団体 特定非営利活動法人 日本心臓リハビリテーション学会
心臓リハビリテーション指導士
- 本委員会主催の講習会を当該年度に受講していること
- 医師、看護師、理学療法士、臨床検査技師、管理栄養士、薬剤師、臨床工学技師、
臨床心理士、公認心理師、作業療法士、あるいは健康運動指導士のいずれかの資格を有していること - 申請時に本学会会員であり、申請時の直近2年以上継続して会員歴があること。
- 心臓リハビリ指導の実地経験が1年以上あること、または心臓リハビリ研修制度により受験資格認定証の交付を受けていること。
- 自験例10例
心臓リハビリテーション上級指導士
(1)申請時に本学会の心臓リハビリテーション指導士資格を 1 回以上更新し、当該年度
の学会費を完納していること。
(2)申請時から過去 5 年間に次の各号のいずれかに該当すること。但し、研究発表及び原著
論文については症例報告を除く。
①本学会の学術集会で筆頭者として研究発表を 1 回以上行い、かつ本学会誌又は査読のあ
る学術誌に心臓リハビリテーションに関連する原著論文又は総説論文(いずれも共著可。)
を 1 編以上発表していること。
② 本学会誌又は査読のある学術誌に心臓リハビリテーションに関連する原著論文又は総
説論文を筆頭者として 1 編以上発表していること。
③本学会誌又は査読のある学術誌に心臓リハビリテーションに関連する原著論文又は総説
論文を共著者として 3 編以上発表していること。
(3)20 例の経験実績(自施設又は関連施設における経験。)を報告すること。
(4)所属長の推薦があること。
詳細は >>>日本心臓リハビリテーション学会ホームページ をご確認ください。
心不全療養指導士
●認定団体 一般社団法人 日本循環器学会
看護師、保健師、理学療法士、作業療法士、薬剤師、管理栄養士、公認心理師、臨床工学技士、⻭科衛生士、社会福祉士
- 実務経験 現在、心不全療養に従事していること
- 入会 必要
- 受験用eラーニング講習受講
- 症例報告書5例
詳細は >>>日本循環器学会ホームページ をご確認ください。
循環器病予防療養指導士
●認定団体 日本高血圧学会、日本循環器病予防学会、日本動脈硬化学会、日本心臓病学会
保健師、看護師、薬剤師、管理栄養士、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、公認心理師、臨床心理士、医療心理士、健康運動指導士
- 実務経験 3年以上の脳卒中や循環器病に関する指導実務経験
- 入会 必要(日本高血圧学会、日本循環器病予防学会、日本動脈硬化学会、日本心臓病学会のいずれか)
- 指定の学術集会等に2回参加
- 下記の①~④のいずれかを満たすもの
① 申請締切日より過去5年以内に下記に2回以上参加した者。(参加を証明できるものを提出)日本高血圧学会総会臨床高血圧フォーラム、高血圧フォーラム日本循環器病予防学会学術集会日本動脈硬化学会総会・学術集会動脈硬化教育フォーラム日本心臓病学会学術集会 ② 認定委員会で定められた講習会および認定委員会が指定したWebセミナー(循環器病予防療養指導士Webセミナー、循環器病予防eラーニング講座の中で循環器病予防療養指導士認定単位が付与されているもの)でA群、B群、C群より合計12単位以上取得した者。(※2) ③ 日本糖尿病療養指導士、腎臓病療養指導士、心不全療養指導士、日本心臓リハビリテーション指導士、腎臓病薬物療法専門認定薬剤師、専門看護師・認定看護師※の資格保持者。
※該当の資格は事務局へお問い合わせください。④ ①,②,③いずれにも該当せず、日本高血圧学会の専門医または評議員、日本循環器病予防学会の評議員、日本動脈硬化学会の専門医または評議員、日本心臓病学会のFJCCまたは代議員のいずれかより循環器病予防療養指導士に値する知識を有する者として推薦され、認定委員会が認めた者。(活動実績を提出) ※1:2025年3月までは受験資格に特別措置を講じています。
循環器病予防療養指導士 | 受験資格 (jpnsh.jp)
※2:(1)受験申請に使用できる単位は、申請から過去5年以内に受講したセミナーが対象になります。
(2)第10回(2025年)認定試験の受験申請においてはWebセミナーでの取得単位数の上限を設けていません。
- 日本高血圧学会のHPは >>>日本高血圧学会ホームページ
- 日本循環器病予防学会のHPは >>>日本循環器病予防学会ホームページ
- 日本動脈硬化学会のHPは >>>日本動脈硬化学会ホームページ
肥満症生活習慣改善指導士
●認定団体 一般社団法人 日本肥満学会
保健師、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、健康運動指導士、 臨床
心理士等
- 実務経験 3年以上の指導経験
- 必要単位 20単位
- 自験例5例
詳細は >>>日本肥満学会ホームページ をご確認ください。
呼吸ケア指導士
●認定団体 一般社団法人 日本呼吸ケア・リハビリテーション学会
初級呼吸ケア指導士
1) 医師・歯科医師 2)看護師 3)准看護師 4)理学療法士 5)作業療法士 6)栄養士・管理栄養士 7)薬剤師 8)言語聴覚士 9)歯科衛生士 10)臨床工学技士 11)臨床検査技師 12)介護福祉士 13)その他、呼吸ケア指導士認定委員会が認めたもの
- 会員歴が連続して36か月以上
- 入会以降に研修単位50点以上
- 非喫煙者
上級呼吸ケア指導士
- 会員歴が連続して60か月以上
- 入会以降に研修単位400点以上
- 非喫煙者
- 初級呼吸ケア指導士有資格者
詳細は >>>日本呼吸ケア・リハビリテーション学会ホームページ をご確認ください。
日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士
●認定団体 一般社団法人 日本摂食嚥下リハビリテーション学会
日本栄養士会との共同認定資格である摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士取得には、「日本摂食嚥下リハビリテーション学会認定士」が必要となっています。
- (1)本学会会員歴が、受験年の7月31日において、2年以上であること。
- (2)摂食嚥下に関わる臨床または研究歴が、受験年の7月31日において、通算3年以上であること。
- (3)日本摂食嚥下リハビリテーション学会インターネット学習プログラム(以下、「eラーニング」という。)全課程の受講を修了していること。
詳細は >>>日本摂食嚥下リハビリテーション学会ホームページ をご確認ください。
日本口腔リハビリテーション学会認定管理栄養士
●認定団体 一般社団法人 日本口腔リハビリテーション学会
- (1)日本国管理栄養士免許を有すること.
- (2)通算5年以上の顎口腔機能のリハビリテーション,摂食嚥下,咀嚼,口腔機能育成,口腔ケア等
- に関する臨床経験を有すること,またはこれと同等以上の経歴を有すること.
- (3)申請時において,連続して2年以上の学会正会員歴を有すること.
- (4)顎口腔機能のリハビリテーション,摂食嚥下,咀嚼,口腔機能育成,口腔ケア等に関する研究報
- 告を行っていること.
- (5)学会の学術大会に参加していること.
詳細は >>>日本口腔リハビリテーション学会ホームページ をご確認ください。
認定褥瘡管理栄養士 / 在宅褥瘡予防・管理師
●認定団体 一般社団法人 日本褥瘡学会
認定褥瘡管理栄養士(褥瘡認定師)
- 国家資格取得後4年以上
- 日本褥瘡学会公認教育セミナー 2回以上(同一年度複数回不可)
- 医療記録10症例
在宅褥瘡予防・管理師
- 国家資格取得後4年以上
- 6時間以上の在宅褥瘡セミナー 1回
- 療養録5症例(2年以内)
詳細は >>>日本褥瘡学会ホームページ をご確認ください。
日本フットケア・足病医学会認定師 / フットケア指導士
●認定団体 一般社団法人 日本フットケア・足病医学会
日本フットケア・足病医学会認定師
- 医療記録10症例
- 日本下肢救済・足病学会、日本フットケア学会、日本フットケア・足病医学会学術集会参加証 3 枚
- 認定師セミナー受講 2回以上
フットケア指導士
- 栄養士資格取得後、3年以上の実務経験を有すること。
- フットケアの実務経験を有すること。
- フットケア指導士認定セミナーを受講していること(認定セミナーの有効期限は2年間)。
- 日本フットケア・足病医学会の学会員であること。
詳細は >>>日本フットケア・足病医学会ホームページ をご確認ください。
骨粗鬆症マネージャー
●認定団体 一般社団法人 日本骨粗鬆症学会
- 本学会会員であること
- 病院・診療所・介護サービス施設/事業所・薬局・臨床検査センター・自治体・保健所・教育機関などに所属して実際に医療・保健・教育活動に従事
- 骨粗鬆症マネージャーレクチャーコース 1回以上受講
- 本学会学術集会 1回以上参加(過去3年以内)
詳細は >>>日本骨粗鬆症学会ホームページ をご確認ください。
栄養経営士
●認定団体 一般社団法人 日本栄養経営実践協会
- 資格認定基礎講習受講
詳細は >>>日本栄養経営実践協会ホームページ をご確認ください。
在宅訪問管理栄養士
●認定団体 一般社団法人 日本在宅栄養管理学会 / 公益社団法人 日本栄養士会
- 日本栄養士会の会員であり、日本在宅栄養管理学会の正会員で管理栄養士であること
- 管理栄養士の登録から5年以上経過し、病院・診療所・高齢者施設などにおいて管理栄養士として従事した日数が通算で900日以上(週休2日と仮定して、3年6か月以上の期間が必要です)であること
詳細は >>>日本在宅栄養管理学会ホームページ をご確認ください。
腎代替療法専門指導士
●認定団体 一般社団法人 日本腎代替療法医療専門職推進協会
- 看護師・保健師, 管理栄養士, 薬剤師、臨床工学技士、移植コーディネーター、および医師の資格を有するもの
- 過去10年以内に通算3年以上、腎臓病患者の療法選択指導業務、食事指導、薬剤服薬指導、移植コーディネート、あるいは腎代替療法の医療現場に従事している者で、各専門または認定資格(注1)を有すること。
- 腎代替療法選択指導に関する20単位(1単位50分)のe-ラーニング講義の受講を行い、各受講単位のe-ラーニング試験に全5問に正解すること
詳細は >>>日本腎代替療法医療専門職推進協会ホームページ をご確認ください。
人間ドック健診情報管理指導士(人間ドックアドバイザー)
●認定団体 公益社団法人 日本人間ドック・予防医療学会
- 医師・保健師, 管理栄養士を有する
- 研修を修了(基礎編・技術編)
詳細は >>>日本人間ドック・予防医療学会ホームページ をご確認ください。
国家資格が不要な資格
国家資格を有しない場合にも、一定の経験や基準をクリアしている場合に、受験資格を得ることができる資格は多数あります。その中で医療の現場ではよく見かける資格を下記にご紹介します。
NR・サプリメントアドバイザー
●運営組織 一般社団法人 日本臨床栄養協会
MRさんが持っているのをよく見かける資格です。当該団体は厚生労働省ホームページにて、アドバイザリースタッフ養成と資格認定を行っている主な団体例として3つ挙げられているうちの一つ。その他、公益財団法人日本健康・栄養食品協会「食品保健指導士」、一般社団法人日本食品安全協「健康食品管理士/食の安全管理士」が挙げられています。
- 実務経験 なし
- 研修 通信教育講座(40単位)
- 入会の必要性 あり
- その他
詳細は >>>日本臨床栄養協会ホームページ をご確認ください。
さいごに
管理栄養士が取得できるステップアップ資格はたくさんあります。他の医療関係職種と一緒に目指せばチーム医療の一助となるでしょうし、管理栄養士独自のものであれば、管理栄養士として一層成長できるかもしれません。まずはどんな資格があるのか知って頂いて、計画的に資格取得を進めていただければ幸いです。各資格の受験資格などの詳細については、必ず公式ホームページをこまめにご確認ください。
今回の記事は学会入会を勧誘するものではなく、入会等にあたっての責任は持てません。熟考の上、各個人の責任で入会・参加をお願いします。また、内容に関しましても、当サイトが責任を持つものではありません。必ず公式ホームページをご確認ください。